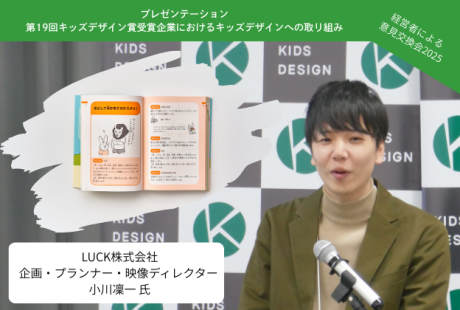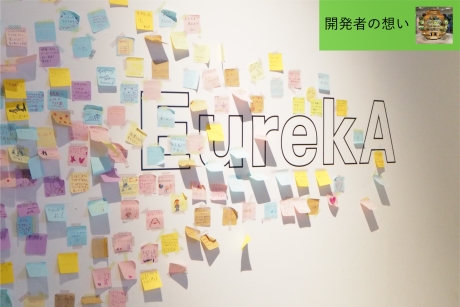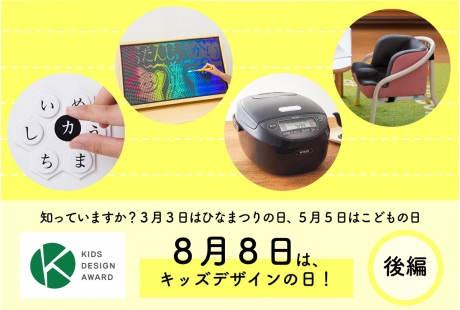2025.9.30
インクルーシブ・キッズデザイン 取材レポート
「子どもの読書とインクルーシブ」NPO法人ピープルデザイン研究所(後編)

キッズデザイン協議会の調査研究事業インクルーシブ・キッズデザインプロジェクトの活動として、インクルーシブな活動「りんごプロジェクト」の取材内容を2回にわたってレポートします。
後編は、読書バリアフリーの重要な発信場所となる「図書館のこれから」についてをご紹介します。
訪問日:2025年5月26日(月)
話し手:
田中真宏 ピープルデザイン研究所代表理事
古市理代 ピープルデザイン研究所理事、りんごプロジェクトの推進リーダー
佐藤聖一 元公共図書館勤務の図書館司書、元日本図書館協会障害者サービス委員会委員長
佐伯美華 横浜市立幸ケ谷小学校 学校・地域コーディネーター
(敬称略)

地域と積極的に連携する図書館こそが、これからの時代に求められる「元気な図書館」と言えるでしょう
こうした中、老朽化した施設を建て替える際に、新たな価値を創造しようとする図書館が増えています。子どもたちが喜んで集まるような工夫を凝らしたり、地域住民の憩いの場となるような居心地の良いデザインを取り入れたりすることで、来館者数を大幅に伸ばしている事例も少なくありません。
また、本の貸し出しだけでなく、子育て中の親が気軽に相談や情報交換ができる場を提供するなど、付加価値の高いサービスを展開し、利用者の裾野を広げているのです。
欧米の図書館は、単に本を貸し出す場所から、地域住民のためのサービス拠点、そしてコミュニティを形成するハブへと進化しています。豊富な資料を活かした勉強会、作家のトークショー、音楽会などを開催するほか、障害を持つ人々も気軽にアクセスできる文化活動の拠点となっている例もあります。来館が困難な人々のために、郵送貸出や移動図書館といったサービスでアクセシビリティを高めることも重要です。このように、地域と積極的に連携する図書館こそが、これからの時代に求められる「元気な図書館」と言えるでしょう。
日本では「読書バリアフリー法」の施行から5年以上が経過し、日本図書館協会が職員研修を行うなどの取り組みを進めています。しかし、全国調査によれば、障害者等へのサービスが一定のレベルに達している図書館は全体の2割にも満たないのが実情です。特に地方では、予算や人員の不足から図書館自体が疲弊しており、課題は山積しています。
北欧の図書館は、あらゆる人々にとって居心地の良い場所でした

特に印象的だったのは、直感的に理解できるサイン(案内表示)です。例えば、日本では「土足禁止」と文字で書かれる場所も、靴のまま入れる場所には靴の絵、脱ぐ場所には裸足の絵が描かれています。これにより、現地の言葉が分からなくても、誰もが一目でルールを理解できます。


※LLブック:「LL」は、スウェーデン語のLättläst(読みやすい)の略語です。短くてやさしい文章や写真、ピクトグラム<絵記号>などで構成されています。
さらに、北欧の図書館は、あらゆる人々にとって居心地の良い場所でした。
赤ちゃん連れの家族が「子どもが騒いだらどうしよう」と心配することなく過ごせる雰囲気があり、親子が声を出して読み聞かせを楽しめます。3Dプリンターで遊んだり、植物を育てたりと、まるで児童館のように子どもが主体的に活動できる環境が整えられています。
1階には市民が相談や手続きができる行政サービスの窓口があります。移民向けの言語学習のクラスもあり、移住先のデンマークやスウェーデンの文化を伝えるだけでなく、移民の出身国のコミュニティをつくって母国の文化や言語も大事にするための勉強会も行っています。
静かに集中できるクールダウン・スペース、開放的なガラス張りのエリア、落ち着ける個室空間など、気分に合わせて場所を選べます。いたるところに置かれたソファやクッションが、誰もがリラックスできる読書環境を提供していました。
スウェーデンのストックホルムの中心地にあるカルチャーセンターは子どもの居場所になっていて、ティーンエイジャーだけが入れるフロアもあります。誰でも無料で使えるキーボードがあって音楽ができるスペースがあったり、 eスポーツができる施設も地下一階にあります。とにかく子どもの居場所や子どもの権利をとても大事にしている国民性だなと思いました。
ヨーロッパでは、まずアクセシブルな電子書籍を制作し、その後に紙の書籍を刊行するという流れが定着しつつあります
電子書籍は、テキストの拡大、音声読み上げ、点字変換などが容易であり、読書におけるバリアを解消する強力なツールです。ヨーロッパでは「読書は基本的人権」という考え方が社会に根付いており、出版のあり方そのものを変えようとしています。
日本では紙の書籍が出版された後に音声化などが検討されますが、ヨーロッパでは、まずアクセシブルな電子書籍を制作し、その後に紙の書籍を刊行するという流れが定着しつつあります。
データ作成自体は比較的容易ですが、不正コピーを防止する著作権管理システムの構築が課題となります。ヨーロッパでは、このシステム開発に多大な投資が行われてきました。
日本でも読書バリアフリー法は成立しましたが、出版社に対するアクセシブルな電子書籍の提供の義務化には至っていません。しかし、その提供は、これまで読書市場から取り残されがちだった人々を新たな読者として開拓する大きな可能性を秘めているのです。
学校図書館と公共図書館の連携によって、子どもたちの学びをさらに豊かにすることができます
しかし、学校図書館と公共図書館の連携によって、子どもたちの学びをさらに豊かにすることができます。
例えば、公共図書館がバリアフリー図書のセットを持っていて、学校図書館に貸し出せないでしょうか。録音図書の全国データベースの利用方法など、学校の教員だけでは把握しきれない専門知識を公共図書館がサポートできます。例えば、データベースから音声をダウンロードしてCDに複製し、読書支援が必要な子どもに提供することが可能です。
さらに、学習の機会均等を保障する上で、文字を読むことに困難がある子どもたちのための「マルチメディアデイジー」の存在を教員や保護者に伝えるだけでも、状況は大きく変わるはずです。
これからの図書館は、地域社会の多様なニーズに応え、あらゆる人々の知的好奇心と学びを支える拠点として、様々な機関との連携を深めていくことが求められています。
お話を伺っての感想
・読書が出来るかどうかでその人の一生が変わってしまう、生涯学習によって人生は広がるということを聞いて、ハッとしました。何かを踏み出すとき、情報や知恵はだれにでも大切です。 読書バリアフリーに限らず、心のバリアフリーは、小さい頃から身に着くといいなと思いました。
・先日、子どもと久しぶりに図書館へ行ったところ、子ども向けの読書スペースの中心に「りんごの棚」がありました。娘も本を探す流れの中で自然とその棚に向かい、点字の本やLLブックを手に取っていました。子どもたちが「特別な本」と意識することなく、さりげなくバリアフリーの図書に触れられる環境があることを、今回初めて知りました。誰かと比べることなく、それぞれに合った読書ができる場所が、いろいろな地域に広がっていることの大切さを感じました。
<インクルーシブ・キッズデザイン プロジェクトについて>
世の中には様々な心のバリアがあります。言語や文化、ジェンダーや性的指向・性自認、ジェネレーション、障害の有無など小さなものから大きなものまで様々です。
子どもたちが多様性と出会い、理解し、受け入れることを通じ、少しでも「心のバリア」を生まない、もしくは取り除くためには何が必要かを考え広めていくために、会員企業のメンバー有志が集まりました。
様々なギャップを超えてインクルーシブな環境づくりに取り組む団体の活動にフォーカスして、主宰者の思いや実践の積み重ねの中から、インクルーシブな環境づくりへのヒントを探っています。
<参加企業・団体>
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ、株式会社フレーベル館、株式会社LIXIL住宅研究所、東京大学大学院